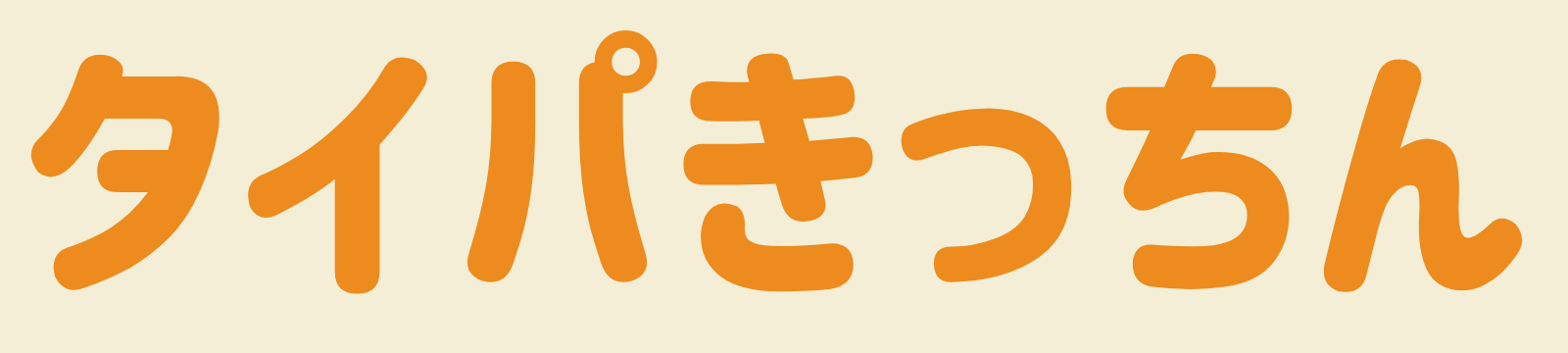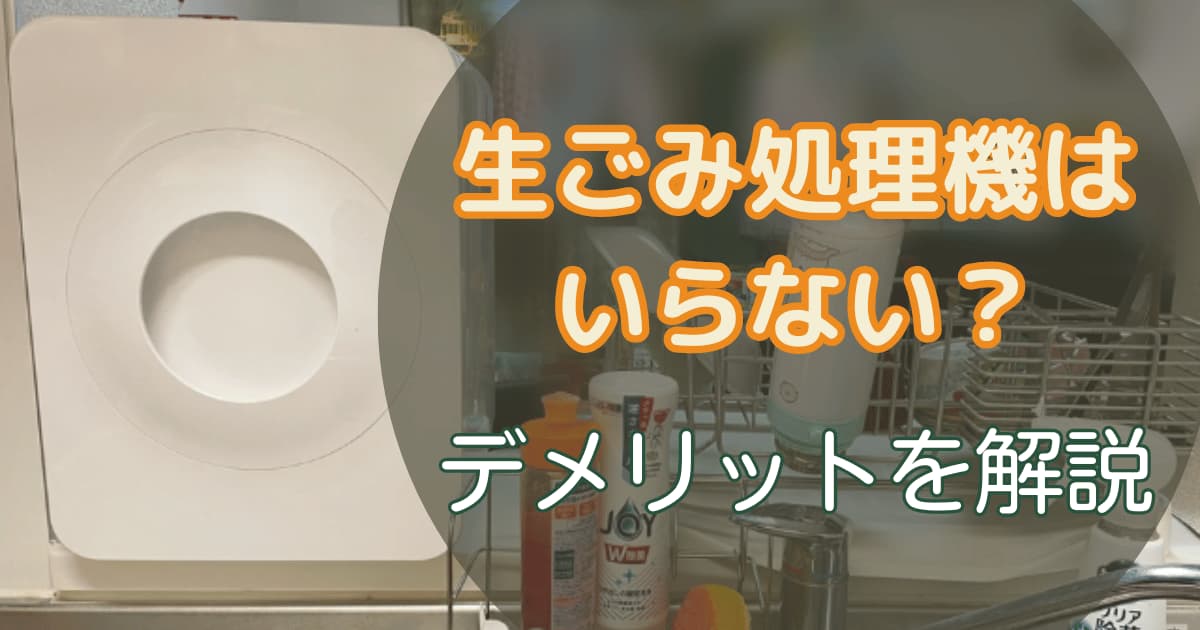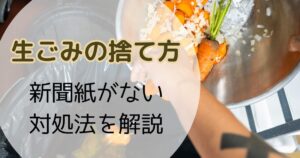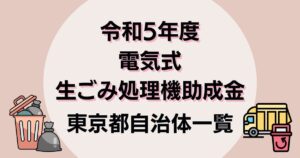生ごみ処理機は、生ごみの排出量を減らすことや、生ごみから生じる臭いを抑えるというメリットがありますが、一方でデメリットも存在し、いらない・買って後悔したといわれるのも事実です。
この記事では生ごみ処理機がいらないといわれる理由であるデメリットとその解決策を解説しています。
主なデメリットは以下の通りです。
- 初期費用の高さ
- 維持費がかかる
- 手入れに手間がかかる
- 稼働時の騒音が気になる
- 設置スペースの確保が必要
- 処理に時間がかかる
解決策としては、補助金の活用、適正な操作と清掃、設置場所の選定や使用時間の設定、キッチンレイアウトの見直し、ごみの分散処理、消耗品の定期補充といった方法があります。
対策をすることで、生ごみ処理機は、生活をより便利で、持続可能なものにし、メリットの上回る商品といえるでしょう。詳しく説明していきます。
\ 世界で120万台売上/
使い勝手の良い
おすすめの生ごみ処理機
公式サイト限定10,000円割引
クーポンコード「loofen」を入力
生ごみ処理機とは
生ごみ処理機とは、その名の通り、生ごみを自宅で処理するための機器です。
毎日の生活で発生する生ごみは大量になるとまとめて処理するのも大変であり、不快な臭いやコバエの原因となることがあります。しかし、この生ごみ処理機を利用することで、これらの問題を解決し、生活環境を快適に保つことが可能になります。
生ごみ処理機のメリット
生ごみ処理機の最大の特長は、自宅で生ごみを処理でき、生ごみを減らすことができることです。このことにより、生ごみ出しの日を気にすることなく、好きなタイミングでゴミを捨てることが可能になります。
さらに、バイオ式(コンポスト式)の生ごみ処理機は生ごみを処理するだけでなく、処理結果として生成される肥料を自宅の庭で利用することも可能です。このため、リサイクルが容易で、環境に優しいというメリットもあります。
生ゴミ処理機の種類
ここでは生ゴミ処理機の種類について解説します。生ゴミ処理機には大きく分けて、「乾燥式」「バイオ式(コンポスト式)」「ハイブリッド式」の3つの方式があります。それぞれの特長や操作方法について紹介します。
乾燥式
熱風を送って生ゴミの水分を蒸発させる仕組みで、数時間で乾燥が完了し、そのままゴミとして捨てられます。
家庭用の生ごみ処理機は、パナソニックの生ごみ処理機、パリパリキュー、ルーフェンなど、この乾燥式のものが多いです。
乾燥させることにより生ゴミの体積や重さが約1/10まで削減され、その結果ゴミ出しの手間や不快な臭いの発生を抑えることができます。
地面に埋めることもできますが、堆肥になるまで時間がかかることが多く肥料として使いたい方には不向きです。
バイオ式(コンポスト式)
生ごみを専用の処理剤(バイオ剤)と混ぜ、微生物を利用して生ごみを分解・発酵させる方法です。
土や肥料を分解し、豊かな土壌を作り上げることが可能で、庭や農地などで活用することができます。必要なのは、微生物を含むスターターと呼ばれるもので、これを定期的に投入しながら使用します。
処理時に腐葉土のようなにおいがするので、屋外に設置して使用することも多いです。
ハイブリッド式
乾燥式とコンポスト式の長所を組み合わせたものが「ハイブリッド式」です。
専用の処理剤と生ゴミを混ぜ合わせて、温風をかけて生ごみを堆肥化する仕組みです。
この方式では、最初に生ゴミを乾燥させてから微生物を用いて発酵させるというプロセスが行われます。この結果、手間をかけずにきちんと処理できるだけでなく、肥料として生ごみを有効活用することも可能となります。
買って後悔しないために生ごみ処理機のデメリットを解説

生ごみ処理機ルーフェンを実際に利用して感じたデメリットもまじえながら、その対策について詳しく説明していきます。
デメリット1:初期費用が高い
生ごみ処理機の導入を考える際、気になるのが初期費用です。高額な商品も多く、一度に大きな金額が必要となり、家計に負担となることもあります。
生ごみ処理機の人気商品の価格は以下の通りです。
| 商品名 | 価格(税込 ) |
| パリパリキュー PPC-11 | 34,980円 |
| ルーフェン | 53,688円(クーポン使用) |
| パナソニック MS-N53XD | 82,588円 |
| ナクスル FD-015M | 127,600円 |
| NAGUALEP NASET-2 | 79,200円 |
機能も様々な商品ですが、乾燥式の安めの商品でも3万円以上します。
このデメリットを克服するためには、長期的な視点でコスト効果を評価すると良いです。
価格が高いと感じるかもしれませんが、これらの機械は一般的に長寿命で、生ごみの処理によりゴミ袋を減らすだけでなく、堆肥作りにも使え、家庭菜園などで土壌改良に役立てることができます。
デメリット2:電気代や活性炭フィルターなどの維持費がかかる
生ごみ処理機は処理に何時間もかかり、その間電気代がかかります。また、多くの製品は、消臭のための活性炭フィルターの交換が必要で、消耗品の定期的な購入が必要です。
これらの維持費の問題は、家計を圧迫し、生ごみ処理機を買って後悔したと感じる原因となります。
デメリット3:手入れに手間がかかる
生ごみ処理機は、定期的に清掃やメンテナンスを行う必要があります。また、部品の交換や修理が必要な場合は追加の維持費用が発生します。また、電気代も無視できません。
しかし、これらの費用と手間を最小限に抑えるための方法もあります。たとえば、使用後はすぐに内部を掃除し、部品の交換が必要になる前に点検を行うことで、高額な修理を未然に防ぐことができます。
デメリット4:騒音問題
生ごみ処理機は稼働時に騒音を発生することがあり、特に静かな住環境に住んでいる場合や深夜に使用する場合は少々気になるかもしれません。
しかし、この問題も克服する方法はあります。例えば、騒音が気になる時間帯には使用を避け、また、機器の設置場所を工夫することで騒音を抑えることが可能です。さらに、最近の家庭用生ごみ処理機fは静音設計が進んでおり、そのような機種を選択することも一つの解決策となります。
デメリット5:使用スペースの確保が必要
生ごみ処理機を導入する際、設置場所を確保することも難点となります。
特に大型の生ごみ処理機を使用する場合、さらにスペースが必要となります。キッチンに余裕がない場合、この問題は深刻となります。
大きなモデルはたくさんの生ごみを処理できますが、実際一般的な家庭ではそれほど必要でない場合が多く、スペースが限られている場合は、より小型のモデルを選ぶとよいでしょう。
デメリット6:処理時間が長い
生ごみ処理機の処理速度や容量も問題となりえます。
生ごみの処理には時間がかかり、大量の生ごみを一度に処理する能力にも限界があるためです。
特に大人数の家庭で、大量の生ごみを出す場合には注意が必要となります。
一度に大量の生ごみを投入するのではなく、分散して投入することや、時間を設定して自動運転を利用することで解決できます。
それぞれのデメリットに対する具体的な解決策を次の項目で見ていきましょう。
生ごみ処理機を買って後悔しないために解決策を解説
前述の1~6のデメリットを解決する対策を考えました。
初期費用の対策:補助金の活用等
品質や機能性の優れた製品は手に入れるだけの価格が必要となります。製品自体の価格が高いという理由で感じる初期費用の高さは、長期的に見れば、生産性向上や省エネなどによる経済性、また製品のセキュリティ性を考慮すれば十分に価値ある投資と言えるでしょう。
高額な初期費用は、自治体の補助金制度を活用することで軽減することが可能です。多くの自治体に補助金制度があるので、確認してみてください。各自治体予算が年度ごとに決まっているところが多いので、早めに申請しないと後悔することに…!お気を付けください。
メーカーや販売店のキャンペーンをうまく利用し、割引で商品を入手するのもいいですね。
維持費の対策:必要経費として予算を組む
電気代や消耗品の購入があるということを事前に確認し、あらかじめ予算を組んでおくことで家計の圧迫を防ぎましょう。
フィルターの交換の有無や価格、交換時期は各メーカーによって違うのであらかじめ調べて維持費の安い機種を選ぶのも方法です。
電気代は省エネタイプの製品が多く、ルーフェンの場合は1日に換算すると約20円と、ノートパソコンの使用電力よりも低いです。活性炭フィルターに関しても、1日当たり25円~50円です。
個人的には生ゴミに関するストレスがなくなることを考えれば安いものと感じます。
メンテナンスの手間の対策:手入れが楽な機種を選ぶ
日々の手入れを怠ると故障の原因となることもあり、こまめなメンテナンスが必要ですが、これが面倒で、買って後悔したと思ったり、時間の経過とともに使わなくなったりということにもなります。
この解決策は、最初から手入れが楽な機種を選ぶことです。例えば生ごみ処理機ルーフェンは、中のバスケットを丸洗いし、本体を拭くだけなので特に手間と感じません。バスケットは食洗機も使えるので面倒な方は食洗機におまかせで大丈夫です。
騒音問題の対策:設置場所の選定や適切な使用時間の設定
騒音問題は、設置場所を工夫すること、または適切な使用時間を設定することで軽減できます。騒音があまり気にならない昼間や早朝に利用するという方法も一つです。
生ごみ処理機の稼働時の音は、その種類や機種によって、大きさが異なります。一般的な家電製品、例えば冷蔵庫などの音は30db程度と言われています。しかし、生ごみ処理機「ナクスル」の音は17.3db~23.2dbと非常に低く、生ごみ処理機「ルーフェン」の音も約30dbと、これらの機種では驚くほど静かな動作を実現しています。図書館の音や、静かな住宅地の音が40db前後です。
もしそれでも音が気になるのであれば、音が気になる静かな夜の利用は避けて、日中に使用するなど使用時間を調整することで騒音の影響を削減することができます。
使用スペースの確保:キッチンのレイアウト見直し等
設置スペースについては、キッチンのレイアウトを見直すことで解決する場合もあります。また、スペースに余裕がない場合は、小型の生ごみ処理機を選択することも一つの手段です。
狭いキッチンで置き場に悩む際の一つの方法は、キッチン以外に設置場所を探すことです。ただし、使用するたびに生ゴミを運ぶのは手間がかかります。
機械を設置する場所に工夫を凝らすことも有効です。例えば、調理器具を収納するスペースを再整理し、機械を置くスペースを作るといった方法です。
また、キャスター付きの台車を購入して、台車の上に置くことで、移動しやすくする方法もあります。この方法なら、使わない時には台車ごとしまうことができ、必要な時だけ取り出して利用することが可能となります。これにより、スペースのことを気にせずに快適に生ごみ処理機を使うことができるのではないでしょうか。
処理時間と容量:最適な機種選び
一般的に、家庭用の生ごみ処理機では生ごみの処理に6~10時間かかります。これは、熱や乾燥、微生物を使って生ごみを分解するために必要な時間です。大量の生ごみを処理する場合、処理時間が長いとそれだけ使用頻度が低下し、結果として処理能力が下がるという問題が生じます。
これを解決する方法としては、まず1つ目に処理時間の短い機種を選ぶことが考えられます。処理時間が比較的短い機種もたくさん存在します。
生ごみ処理機はコンパクトな寸法で設計されているため、一度に処理できる生ごみの量は限られています。特に大家族で大量に生ごみが出る場合、容量が足りないという問題が生じ、結果として生ごみが溜まってしまうことがあります。
その対策としては、生ごみの出るタイミングを考えて、毎日一定量を処理するようにすることで、処理機の負荷を軽減することが可能です。さらに、生ごみを減らす工夫をすることも考慮に入れましょう。余計な皮を剥いたり、食べ残しを減らしたりするだけでも生ごみの量は大幅に減らせます。
後悔しないための生ごみ処理機デメリットまとめ
生ごみ処理機は、家庭内でのゴミ問題解決に対する有効な手段となります。しかし、今回あげたようなデメリットが存在し、買ったことを後悔する可能性があるのも事実です。
以上のようなデメリットがあるとはいえ、生ごみ処理機は環境負荷の軽減やキッチン周りの衛生維持に大いに役立つ便利なアイテムです。そして、それらのデメリットも正しい知識と対策によって、大きな問題にはならないはずです。生ごみ処理機を上手に使いこなし、快適な生活空間を手に入れましょう。
実際に生ごみ処理機「ルーフェン」を使用して感じたデメリットやルーフェンの口コミはこちらの記事にまとめています。
生ゴミ処理機ルーフェンの口コミと正直レビュー|デメリットも解説
\ 世界で120万台売上/
お急ぎください
今月注文分残りわずか!
公式サイト限定10,000円割引
クーポンコード「loofen」を入力